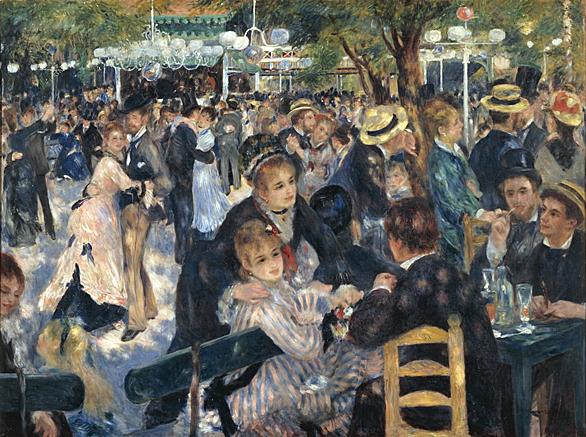三十年戦争
ドイツ30年戦争とも呼ばれる。ただし単一の戦争が30年続いたわけではなく、現在のドイツを舞台に連続して行なわれた複数の戦争を一まとめにして30年戦争と呼ぶ。
新教徒の反乱を契機として始まり、宗教戦争の側面を持ちつつも、諸外国が自国の利益を求めて次々に介入、欧州諸国の大半を巻き込む大戦争となった。戦争の結果、神聖ローマ帝国はほぼその実態を失い、スペインも大きく力を失い、代わってフランスの力が伸張した。
概要
- 年代:1618年〜1648年
- 主要参戦国
- 新教(反ハプスブルク)側:ボヘミア、ファルツ、スウェーデン王国、フランス王国、ネーデルラントなど
- 旧教(ハプスブルク)側:神聖ローマ帝国、スペイン王国、バイエルンなど
- 両方:デンマーク王国、ザクセンなど
- 講和条約:ウェストファリア条約(1648年)
- 主な期間
- ボヘミア・ファルツ戦争期(1618年〜1623年)
- デンマーク戦争期(1625〜1629年)
- スウェーデン戦争期(1630〜1635年)
- スウェーデン・フランス戦争期(1635年〜1648年)
以下は(小説風の)戦争の経緯
1 ボヘミア・ファルツ戦争
マルチン・ルターの宗教改革以後、プロテスタントを奉じる諸侯はウニオン(連合)を結成し、カソリック側はリーガ(同盟、旧教同盟)を組織して、民衆を巻き込んだりしつつ激しく争った(シュマルカルデン戦争)。アウグスブルクの和約で一応の和平はなったが、その本質は問題の抜本解決ではなく先送りであった。もっとも、諸侯の本当の目的は自家の勢力拡大にあって宗教的な問題の解決にはないのだから、それで問題ないといえばその通りだった。
神聖ローマ帝国領ボヘミアはフス以来の伝統を誇る宗教改革の土地であり、独自の気風を有するが、同時に豊かな産業地帯でもあった。このため、ボヘミア王を兼ねるルドルフ帝も、それに続いたマティアス帝も、比較的穏健な宗教政策で臨んでいた。
だが、フェルディナントが1617年にボヘミア王に選出されると事情が変わってくる。彼は反宗教改革の総本山たるイエズス会で教育を受けた熱心党とも呼ぶべき存在だった。圧迫を受けた新教徒たちはついに1618年5月22日、ハプスブルクの代官2名を市庁舎の窓から突き落とした。
皇帝マティアスは穏健な解決策を模索していたが、当事者のフェルディナントは妥協して事態を終わらせるつもりはなかった。どのみち、ボヘミア側にとっても、ここで一時的に休戦してもマティアス没後にフェルディナントが皇帝に就任したら事態がさらに悪化するのは目に見えていたとも言える。
フェルディナント側の軍勢がボヘミアに侵入するが、ボヘミアの新教貴族たちは連合してこれに当たり、撃退に成功する。また、ボヘミア側が期待していたフランス王国(旧教国だがブルボン家は反ハプスブルクの筆頭格だった)の援助は得られなかったが、ファルツ選帝侯とサヴォイア公が組織したマンスフェルト麾下の傭兵軍がやってきてくれた。
1619年3月、マティアス帝が没した。勢いづく新教勢はウィーンを攻撃したが、これは撃退される。
8月、新皇帝にフェルディナントが選出された。新教側の選帝侯もファルツを除けば皆フェルディナントに投票していた。一方、新教側には新たにトランシルバニア公が参戦し、また、ボヘミア人たちは(フェルディナントに代えて)ファルツ選帝侯フリードリヒをボヘミア王に選出した。前者はともかく、後者は各地に波紋を投げかけた。フリードリヒの勢力伸長を喜ばぬ諸侯は反乱に敵対的な方向に動く。中でもバイエルン大公のマクシミリアンは旧教同盟の盟主として、ティリー率いる大軍を組織して、皇帝側に立って参戦した。
1620年11月8日、プラハ近郊で会戦が行われた。わずか1時間でボヘミア軍の戦列は崩壊、フリードリヒは逃亡した。(1年ちょっとで王位を失ったことで、Winterkonig「冬王」と呼ばれる)。
皇帝はプラハ及びボヘミアに対して苛烈な報復を行い、以後ボヘミアでの新教は大いに衰えた。このときに没収された新教貴族の領地を買い集めて大領主に成り上がったのがヴァレンシュタインである。
ここで戦争が終わってもよかったのだが、皇帝に味方するスペイン軍はライン川流域のファルツ領を制圧しており、これはオランダ(ネーデルラント)にとっては無視できない脅威であった。また、皇帝はファルツ選帝侯位をバイエルンに報償として与えようとしたので、やはり諸侯の反発を招いていた。
そこで、オランダはデンマークと語らって逃亡中のフリードリヒに援助を与え、また、ブラウンシュヴァイクやバーデンといった諸侯も反皇帝に立って参戦した。この時点の皇帝は自前の軍隊を持たなかったが、スペイン勢と選帝侯位に虹を見るバイエルンが味方だった。何度かの戦闘や新教側の内輪もめがあったが、最終的に1623年に旧教同盟軍を率いるティリーがフリードリヒ軍を壊滅させたことで決着した。
2 デンマーク戦争
ハプスブルク家の勢力伸長は、他国にとっての脅威に他ならない。ことにスペインと独立戦争を直接戦っているオランダと、スペインとドイツに挟まれているフランスにとっては、深刻な問題だった。
1624年1月、リシュリュー枢機卿がフランスの宰相となった。彼は反ハプスブルクを推進するため、蘭英瑞丁といった諸国に加え、さらにローマ教皇領との提携を図った。
最初の戦略目標は北イタリアからスペイン領ネーデルラントに繋がる連絡線、スペイン道である。この、ジェノヴァとミラノから発し、アルプスを越えてライン川を下る交通線が、オランダで戦うスペイン軍を支えていた。そもそも、ファルツの領土の半分(ラインラント・プファルツ)がその交通線の真上に位置していたがためにスペインによって制圧されたといった面もある。フランス側の策謀によってスイス南東部の新教徒が蜂起したことでスペイン道は断たれた。
つづいて、帝国内への領土的野心を持つデンマーク王クリスティアン4世が参戦する。
1625年、国王直率のデンマーク軍が北ドイツに侵入。これに呼応してマンスフェルトの傭兵軍なども立ち上がる。一方、皇帝はスペインとの連絡を失い、バイエルンの組織する旧教同盟軍(指揮者はティリー)しか頼るものがない。自前の軍事力も戦費にも事欠く皇帝の前に、タダで皇帝軍を組織してみせると豪語する人物が出現した。史上最大の戦争企業家、ヴァレンシュタインである。
ヴァレンシュタインは出資を集めたり自弁したりして費用を賄い、たちまち兵力2万の傭兵軍を組織した。この時点での両軍の主な野戦軍は以下のような陣容だった(=指揮系統や補給などの問題から、野戦軍相互の合一や連携は極めて困難だったため、それぞれ別々の場所にいた)。
- 新教側
- デンマーク軍(国王クリスティアン4世指揮)
- 新教側傭兵軍(隊長マンスフェルト指揮)
- ブラウンシュヴァイク軍(公子クリスティアン指揮)
- 旧教側
- 旧教同盟軍(ティリー指揮)
- 皇帝側傭兵軍(ヴァレンシュタイン指揮)
最有力の新教側諸侯である、ザクセンもブランデンブルクも、この時点では動いていない。いずれも、反ハプスブルクを唱える他国が介入してきたからといって、それにうかうかと乗るつもりはなかった。
かくてティリーはブラウンシュヴァイク軍を破り、一方ヴァレンシュタインはマンスフェルトの軍を破った。
残るデンマーク軍も、1626年8月27日にルッターの会戦でティリーによってさんざんに打ち破られた。デンマーク軍は大砲すべてを鹵獲され、文字通り壊滅的な打撃を受けた。マンスフェルト軍も指揮の乱れから崩壊し、北ドイツ一帯は旧教軍の草刈り場と化した。
デンマーク軍の守備隊を撃破した後、ヴァレンシュタイン軍はデンマーク本土であるユトランド半島に侵攻し、残存するデンマーク軍は大陸を放棄して脱出した。ヴァレンシュタインはデンマークを完全に屈服させるべく海軍の建設に乗り出そうとした。これは成功しなかったが、デンマークはもはや限界であり、1629年6月のリューベック条約で戦争から脱落した。
終戦に先立つ1629年3月6月、皇帝フェルディナント2世は回復勅令(Restitutionsedikt(独)。回復令、復旧令ともいう)を発していた。内容を一言で言うと、「新教のものは旧教のもの、旧教のものは旧教のもの」であり、各地の教会領を正統な持ち主、つまりカソリック教会のもとへと返還することが定められた。ドイツの新教諸侯にとっての宗教改革とは、ローマのくびきからの自由と教会領土の世俗化(=世俗権力によって教会領を支配すること。平たく言えば強奪)を意味していた。回復勅令とは、つまりはその全否定に等しい。
ついでに言えば、教会領土が回復されればそれに付随して大量のカトリックの聖職者を送り込むことができるわけであり、教会を経由する形で皇帝の力が大幅に伸張することになる。
とは言っても、ヴァレンシュタイン麾下の皇帝軍は今や10万を軽く超える規模に達しており、それに正面切って逆らえる者はほとんどいなかった(現実主義者のヴァレンシュタイン自身は、この勅令には批判的だったされる。)。
フランスはそれまで、国内でいわば国家内国家を有していた新教徒勢力との内戦を戦っていた。彼らはユグノー戦争(1562年〜1598年)という形で一足早く「三十年戦争」を経験しており、それゆえ国内の統合を優先していた。したがって戦争中は国外に手を伸ばす余地に乏しかったが、ついに1628年10月に新教徒側の最後の拠点であるラ・ロシェルを陥落させて王権の支配を確立した。
フランスは北イタリアでマントヴァ公国の支配を巡ってスペインと争っている最中(マントヴァ継承戦争。1628年〜1631年)であり、反ハプスブルクにテコ入れを行うべき頃合いだった。教皇も、自領にほど近いマントヴァにスペイン勢が入ったことで敵対的な反応を見せ、回復勅令を認めないと言い出していた。
まずリシュリューはポーランド王国とスウェーデン王国の戦争を調停して終わらせた。新教国スウェーデンに多額の財政援助を約束して、ドイツへの介入を実施させるためである。また、デンマーク戦争中にヴァレンシュタインの脅威を受けた沿バルトの都市群(=旧教側がデンマークを完全に屈服させるためにはバルト海の制海権が必要だったが、そのための基地獲得を目的としたヴァレンシュタインの攻撃を受けていた)も、やはりスウェーデンに同心する構えを見せた。
帝国内の旧教諸侯にしても、皇帝権力の過度の強大化は望ましいことではなかった。まして教皇までもが回復勅令を認めないと言ってることで、なおさら反発は高まっていた。
諸侯の反発心はとりあえず皇帝の発言力を担保しているヴァレンシュタインに向けられた。1630年7月、選帝侯たちは一致してヴァレンシュタインの解任を要求した。次の皇帝を実子フェルディナント(後のフェルディナント3世)としたい皇帝は選帝侯たちの意向を無視できないし、また、ヴァレンシュタインの力の強大化はもはや一介の傭兵隊長の域を超えていた。事態を見るに敏なヴァレンシュタインは、職を辞すと自領へと隠遁した。
3 スウェーデン戦争
3.1
1630年7月4日、「北方の獅子」グスタフ・アドルフは精兵スウェーデン軍を率いて北ドイツ、ポンメルンに上陸した。
旧教側の認識では、スウェーデンは北方の辺境国であって、その戦力は取るに足りないものだった。実際には、いち早く新教を国教化したスウェーデンは、辺境故に信仰心に篤い国民を抱えており、また、その軍事制度はマウリッツ以来の軍事革命の先端を走る画期的なものだった。そして総帥たるグスタフ・アドルフ王の軍事的才能も恐るべきものだった。
ドイツに上陸したスウェーデン軍は、まずは周囲の足場がためを行った。しかし、グスタフらが期待していたドイツの新教諸侯はなかなか動かず、わずかにマクデブルク市などが同盟に応じただけだった。同年中はそのまま小競り合いに終始するが、旧教側のティリー軍は補給がうまくいかず、疲弊しつつあった(本来の策源地がヴァレンシュタインの領土に含まれており、彼が補給をサボタージュしたことが原因とも言われる)。
年が明けて1631年4月になって、回復勅令の取り消しを拒否されたザクセン選帝侯(新教)はついに中立を捨てて反皇帝側に立つことを決意する。傭兵隊長フォン・アルニムを雇用、新たな軍の編成に乗り出した。
一方のティリー軍は物資の不足が深刻化し、とてもスウェーデン軍とは戦えない状況に陥っていた。そこで彼らはまずは手近なマグデブルク市を攻略してそれを手に入れようとした。
グスタフ・アドルフは新教側諸侯と合同してからティリー軍との決戦を行うつもりであったが、同盟者を見捨てるというのも宜しくないので、マクデブルクの救援に向かった。が、時すでに遅く1631年5月20日にマクデブルクは陥落した。
ティリー軍の兵士たちは市内で虐殺と掠奪を繰り広げ、市の人口3万人中2万5千人が殺害されたと言われる。この結果、皇帝軍の評判は大暴落し、プロテスタント諸侯は陸続とスウェーデンとの同盟に向かう。ティリー軍は物資を求めてドイツ各地を放浪し、ライプチヒに入る。
9月17日、ライプチヒの近郊ブライテンフェルトでティリー軍とスウェーデン・ザクセン連合軍が激突した。ザクセン軍は撃破されたものの、精鋭スウェーデン軍はティリー軍に壊滅的な打撃を与えることに成功した。
越冬したスウェーデン軍は翌年に戦役を再開。1632年4月15日のレヒ河畔の戦いでスウェーデン軍はティリー軍を捕捉し、ついに皇帝軍総司令官ティリーを敗死させた。皇帝軍は崩壊し、頼みのスペイン軍もネーデルラント勢との戦いに忙殺されており、助けにこれない。
3.2
罷免された後のヴァレンシュタインは自領で悠々自適の毎日を送っていた(占星術に凝っていたヴァレンシュタインは、復職できるとの卦が出ていたので安心していたとも言われる)。絶体絶命の皇帝は、ここで高値を覚悟の上でヴァレンシュタインの再登用に踏み切る。完全な売り手市場であることを理解していたヴァレンシュタインは、相当にふっかけた上で復職に応じた(詳しい条件は不明。和戦の決定権を含む全軍事権や選帝侯位といった破格の条件であったとされる)。
たちまち大軍を組織したヴァレンシュタインは、まずは外交交渉でザクセン軍を退去させることに成功し、さらに遠征軍の弱点を持つスウェーデン軍の足下を各種の外交的手段でゆさぶる。つづいて、ニュルンベルクに籠城したスウェーデン軍を包囲し、十分な防護を固めて決戦を避けた上で補給線を脅かす。補給不足に苦しむスウェーデン軍は堅固な攻囲軍の陣地を攻撃するも、大損害を受けて撃退された。スウェーデン軍の無敵伝説はここに払拭され、戦争のイニシアティブは皇帝軍へと移る。
その後、ザクセン領を巡る機動の末に、ついに両雄の激突の機会が訪れた。1632年11月16日、リュッツェンの戦いがヴァレンシュタインとグスタフ・アドルフの決戦となった。戦いは凄惨なものとなった。乱戦のさなか、グスタフ・アドルフ王は戦死。しかし王の死に憤激したスウェーデン軍は却って攻勢に出る。一方皇帝軍の猛将パッペンハイムも戦死し、こちらの配下部隊は潰乱する。このため皇帝軍の本陣も蹂躙される事態となり、ヴァレンシュタインは退却を余儀なくされた。一方、総帥を失ったスウェーデン軍もこれを追撃せず、戦いはスウェーデン軍の一応の勝利で終わった。
とはいうものの、総司令官を失った新教軍は著しく戦略的に劣勢になった。
3.3
スウェーデンは幼少のクリスティナ王女を補佐する宰相オクセンシェーナ(Axel Gustafsson Oxenstierna(1583年〜1654年)ウクセンシェルナとも。スウェーデン史上最大の政治家。カール9世の大臣を経てグスタフ・アドルフの宰相となる。王の死後の最高指導者)が、(フランスの援助を受けつつ)新教諸侯との同盟を結成して戦争を続行することを決意。一方でザクセン選帝侯は(所詮は外国であるスウェーデンに頼りすぎるのを避けるべく)単独講和を模索する。
引き続き最有力の部隊を率いるヴァレンシュタインは各地のスウェーデン軍守備隊を撃破するが、一方では和平を模索する動きも見せる。一応の危機を回避した皇帝にとっては、(もともと危険視している)ヴァレンシュタインを排除せねばならないとする動機となった。未だ参戦していないフランス王国もヴァレンシュタインと皇帝の離間を画策する。
一方で決断力を失って迷うヴァレンシュタインは決定的な行動に出ることなく時間を浪費する。ついに皇帝はヴァレンシュタインの排除を決定、逃亡したヴァレンシュタインはあっさりと皇帝の放った刺客の手にかかり暗殺された。
代わりの皇帝軍総司令官には皇帝の長男のフェルディナントが就任、ヴァレンシュタイン配下の隊長たちも彼に従った(=ヴァレンシュタインは軍制改革を行い、従来の傭兵軍の枠を越える常備軍の萌芽と言えるものを形成したが、その結果、個人でなくシステムによって軍が支配される状況を作り出してしまった、とも言える)。
3.4
スウェーデン軍と皇帝軍の直接対決は、1634年9月6日、ネルトリンゲンで行われた。結果は皇帝軍の大勝利に終わる。スウェーデン軍は壊滅し、皇帝軍は一気に占領地を拡大する。疲弊した各交戦国は和平を模索する。こうして1635年5月にプラハ条約が結ばれる。皇帝は回復勅令の撤回に応じ、領土を安堵されたザクセンはこれを受け入れて和平に応じた。代償に、ザクセン候は独自の同盟権を放棄し、皇帝の覇権を認めることとなった。様々な政治的術策を用いて皇帝はこの条項を他の帝国諸侯にも飲ませることに成功する。最後まで渋っていたバイエルンも皇帝に懐柔されてこれを了承して旧教同盟(リーガ)を解散、ここに皇帝は神聖ローマ帝国内の真の第一人者となった。
4 フランス・スウェーデン戦争
フランス王国は、戦争の開始当初から反ハプスブルク側の最大の黒幕として、陰に陽に新教勢力を支援していた。同時に近隣のハプスブルク領、ネーデルラントや北イタリアなどへの領土的野心も有していた。ドイツでの戦争がハプスブルク家の勝利に終わりそうな今、もはや事態を転回させるにはフランスが直接参戦する以外になかった。1635年、フランス王国は反ハプスブルク陣営に立って参戦する。
リシュリューおよび後継者のマザランはカタロニア、北イタリア、ライン流域、ドイツ内部、でハプスブルク家の軍勢と戦い、手ぶらで帰れぬスウェーデン軍も死にものぐるいで戦い続けた(戦乱の連続から、スウェーデン本国の疲弊も深刻な物であり、なんらかの戦果と有利な講和条件を得ることが至上命題だった。)。
カソリック国フランスが新教側に荷担するというこの事態は、まさに従来の常識を覆す「まったく新しい戦争」だった。このため戦争はより国益をむき出しにしたものとなり、新教側だったデンマーク王国が皇帝側に立って参戦したり、オスマン帝国が戦争に介入するなど、非常に複雑な動きを見せた。
各国とも戦争によって大いに疲弊していたが、勝利者となったのはフランスだった。三十年戦争後半期最高の将帥、コンデ公に率いられたフランス軍は、1643年にロクロアでスペインのエリート歩兵を撃破し、スペインの軍事力の中核を崩壊させる(この軍事的損失からスペインは回復できず、1640年のポルトガル独立と相まって、覇権獲得能力を大いに失墜させた)。
もはやドイツ諸侯も皇帝もスウェーデンも、もはや戦争に倦んでいた。1644年から和平交渉が開始された。だが、和平交渉で優位に立つためには戦勝が必要である。戦争を終わらせるためにさらなる軍事行動が求められるという状況が発生する。
いくつもの会戦が行われたが、フランス軍と復活したスウェーデン軍の優位は明らかだった。ザクセン、バイエルンと皇帝側の諸侯は次々と戦争から脱落。皇帝側で再参戦したデンマークも、スウェーデンに敗北して退場した。ついにスウェーデン軍はすべての始まりの地であるボヘミアへと侵攻、プラハを攻囲する。
一方、1648年8月のランスの戦いでコンデ公はまたも勝利を収め、ここに皇帝側は万策尽きた。フランス軍を掣肘する手段もないし、プラハが陥落すれば帝都ウィーン(カール大帝以来の移動宮廷の伝統に代わり、恒久的な宮廷所在地となっていた)も風前の灯火である。が、一方のスウェーデンはもはや国力の限界に達しており、フランスも後に「フロンドの乱」と呼ばれる大内乱の勃発が目前まで来ていた。双方の思惑はここに一致し、ヴェストファーレン地方で行われていた和平交渉がついに決着、1648年10月24日、「ウェストファリア条約」が締結された。戦争は終わった。
5 ウェストファリア条約
戦争はなにしろ前代未聞の大戦争であり、参戦国の数も膨大なものであった(代表を送り込んだのは60カ国以上で、史上初の大規模国際会議であると言える。イングランドを除くヨーロッパの主要国は、ほぼ全員が当事者だった)。
完全征服といった分かりやすい決着が不可能な以上は話し合いで決するしかないが、当然ながら利害の調整は難航していた(威信と直結する問題である、席次や条約に署名する順序自体が揉める一因となった)。
ともかく、講和条約はそれぞれの当事者間で様々な条件で結ばれた。条約調印の舞台となったのはヴェストファーレンの二つの都市、ミュンスターとオスナブリュックだった。
1648年にオランダはスペインと講和し、彼らのスペインからの独立が正式に認められた。
10月24日、帝国とフランス、帝国とスウェーデンでそれぞれに講和条約が成立し、戦争の主要部分は(フランスとスペインの戦争を除いて)終わった(ただし、通信手段が未発達な時代なので、和平の知らせが入った11月まで、プラハの攻囲は継続されていた。戦争の始まりの場所が、最後まで戦闘が続いた場所ともなった)。
条約の結果、神聖ローマ帝国内での「信教の自由」が確認された。諸侯は自らの宗教を決める権利を有し、新教諸侯も旧教諸侯と同等の扱いとなる。これだけならばアウグスブルクの和約の確認とも言えるが(今回はルター派だけでなくカルヴァン派の権利も認めているので、その点は異なる)、のみならず、全諸侯は皇帝選挙権(選帝侯)を除けばすべて同等の地位を認められ、内外政を自由に行えることとなった。皇帝の目指した統一の夢はここに破れることになる。皇帝の権威とか帝国裁判所とかそういったまとまりは残されたものの、事実上の「帝国の死亡証明書」であった。
諸国分立が公認されたことと戦乱による荒廃とで、ドイツの近代化は大幅に遅れることとなった。ハプスブルク家は名目的な皇帝位を保持し続けたが、オーストリアを中核とする多民族の領域国家(それはそれで一つの「帝国」ではある)として再生していくことになる。
勝利者であるスウェーデンやフランスは帝国内に領土を獲得、後々の(あるいは直近の)紛争のきっかけともなった。
フランスはスペインと戦争をつづけ、同時に「フロンドの乱」という巨大な内乱を経験する。リシュリューの後継者たるマザランはその解決に全力を投じ、1659年のピレネー条約によって戦争を終結させると、その2年後に亡くなっている。ルイ14世が以後親政を行い、スペインの果たせなかった夢、ヨーロッパの覇権に挑むことになる。
スウェーデンはバルト海の両岸にまたがる領土と制海権によって「バルト帝国」を築き上げ、ブランデンブルク選帝侯などと戦いつつも、17世紀に全盛期を迎えた。